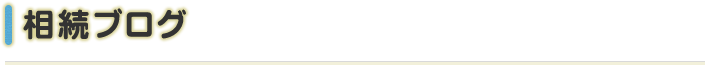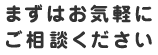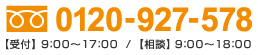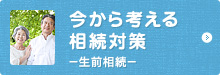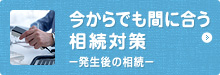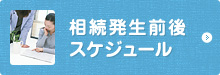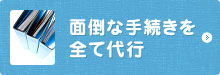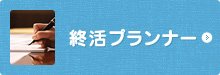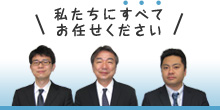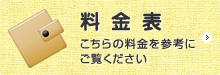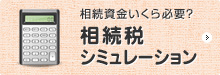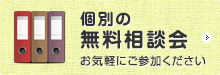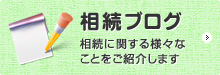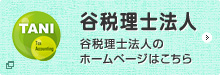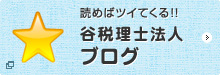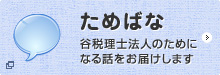1 最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等が請求可能になります
戸籍謄本等の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになる制度です。
2024年3月1日(令和6年3月1日)からこの制度を利用することが可能になりますが、この制度が始まることによって、本籍地の窓口に請求する必要がなくなるため、最寄りの市区町村の窓口で戸籍等の請求が可能になります。
また、全国各地の戸籍謄本等を取得できるため、手続に必要な戸籍を1ヶ所の窓口でまとめて取得することも可能となります。
2 広域交付で取得できる戸籍等の範囲
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍等を取得することができますが、広域交付制度では、きょうだいの戸籍を取得することはできません。
きょうだいの戸籍が必要な場合には、これまでどおりに本籍地の窓口に請求するか、専門家などに依頼して取得する必要があります。
3 広域交付に関するその他の注意点
広域交付制度を利用するためには、戸籍謄本等を取得しようとする本人が窓口に行って手続をする必要があります。
また、窓口で請求する際には、本人確認書類が必要となりますので、ご注意ください。
本人が窓口に行って請求をすることになっていますので、郵送での請求や、専門家などの代理人が代わりに窓口に行って利用することはできませんので、効率よく戸籍謄本等を取得する方法を専門家などともよく協議する必要があります。